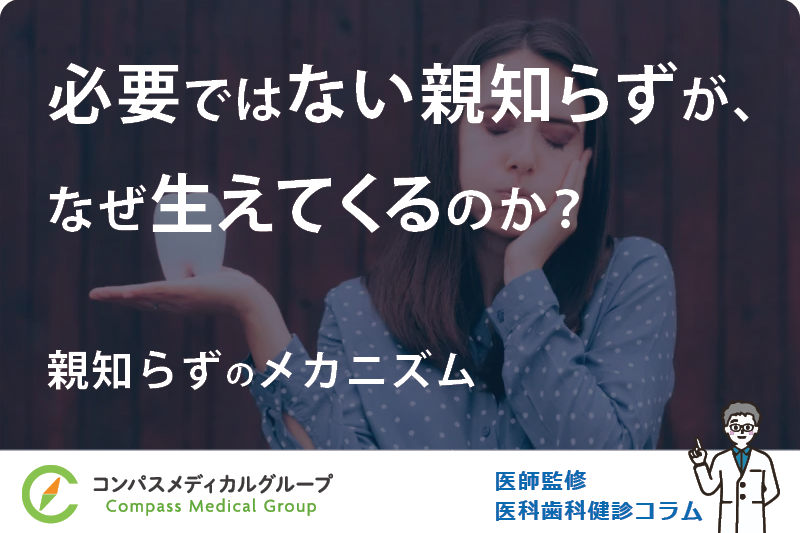親知らずと呼ばれる歯について
一般的に親知らずと呼ばれる歯は、歯の一番奥に生える永久歯のことで、智歯(ちし)や第三大臼歯とも呼ばれます。一般的に15歳~18歳くらいから親知らずは生えてくるといわれていますが、必ずしも誰もがきれいに見えるように生えるとは限りません。
というのも、親知らずが正常に生えてくる確率が低いからです。親知らずは生えてきても完全な形で生えることはまれで、斜めに生えたり不完全の状態のままだったりします。そうなると歯肉に炎症がおきて腫れと痛みを伴うばかりか、歯並びが悪くなるケースもあります。
親知らずが生える際の痛みについて
親知らずが生える際には、横向きに生えるケースが多く、腫れや痛みがなくても歯みがきがしづらい部分にあるため、周囲の歯肉に炎症(智歯周囲炎)を引き起こし、痛みを感じることもあります。また、見えていなくても歯茎の下にある事もあり、知らず知らずのうちに手前の歯を虫歯にしたり、親知らず自身が虫歯になる事が多々あります。親知らずと呼ばれる第三大臼歯は、なくても身体には問題のない歯なので、ほとんどの場合に第三大臼歯は抜歯されます。では、必要でない親知らずが、なぜ生えてくるのか不思議に思われるでしょう。
親知らずのメカニズム
最後に生える永久歯
ここからは、親知らずのメカニズムについてお伝えします。親知らずは先にお伝えしているとおり、歯の一番奥にある第三大臼歯と呼ばれる歯です。小学生時代に親知らずが生える方は少なく、中学生から高校生時代に生えることが多いです。その理由は、第三大臼歯は最後に生える永久歯なので、高い年齢になって生えることとなるからです。人によっては、20代前半で生えてくることも珍しくありません。そのため、親に知られることなく生えてくるので「親知らず」と呼ばれるようになったといわれています。親知らずは生えない方もいますが、基本的には上下に各2本、合計4本生えてきます。
大昔は必要だったが、現代では不要

元々昔の人間にとって第三大臼歯は必要な歯で、正常に生えてきていたのです。昔といっても大昔のことになりますが、当時の食材は木の実や動物の生肉、穀物など硬い食材ばかりです。そのため、あごの骨も発達しており親知らずが生えるスペースがしっかり確保されていました。ところが、現代では大昔ほどの硬い食材を食べることがなくなったので、それに合わせてあごの骨が未発達となり親知らずが正常に生えるスペースがなくなってしまったのです。このように、大昔では必要とされていた親知らずですが、現代では抜いた方がよい歯と変ってきています。